バイクのヘルメット着用の法的義務

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/A4-264220/
ヘルメットは万が一転倒した際に、頭部を守ってくれる重要なアイテムですが、バイクで走行する場合はヘルメット着用の法的義務も生じます。
バイクのヘルメット着用義務を定めた法律と罰則、よくある誤解について解説をしていきます。
道路交通法 第71条の4
道路交通法の第71条の4は、バイクを運転する際にヘルメット着用義務がある根拠となる条文で、以下のように定められています。
「大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。」
引用元:e-Gov
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
大型自動二輪と普通自動二輪を運転する際、乗車用ヘルメットを被らずに運転することができないと定められており、次の2項では原付にもヘルメットの着用義務があることが定められています。
このように道路交通法 第71条の4は、原付であっても大型バイクであっても、二輪車で公道を運転する場合は、ヘルメットの着用義務があるということが定められた条文です。
バイクで道路を走る際はこの条文が根拠となり、ヘルメットの着用義務が発生し、ヘルメットを着用せずに走行すると法律違反となります。
対象となる車種
二輪車でヘルメットの義務がある対象となる車種は、以下の通りです。
| 車種 | ヘルメット義務 | 備考 |
| 原動機付自転車(~50cc) | 必須 | 原付一種 |
| 小型二輪(51cc~125cc) | 必須 | 原付二種 |
| 普通二輪(126cc~400cc) | 必須 | 二人乗りも要着用 |
| 大型二輪(401cc~) | 必須 | 高速道路の利用もあり、安全性が特に重要 |
バイクで公道を走行する場合は、50ccの原付バイクであろうと、400ccを超える大型バイクであろうと、全てのバイクにヘルメット着用の義務があります。
二人乗りができるバイクで二人乗りをする場合は、運転者のみならず後席に乗せる人にも、ヘルメットの着用義務が生じ、守らなければ交通の違反取締り対象です。
中でも高速道路の走行が可能な125ccを超える排気量のバイクは、より高い速度での走行ができるため、フルフェイスやジェットヘルなど、安全性が高いヘルメットの着用が推奨されています。
違反時の罰則
バイク走行時にヘルメットを着用しないで警察官の取締りにあった場合、以下のような罰則を受けます。
| 内容 | 対応 |
| 違反名 | 乗車用ヘルメット着用義務違反 |
| 違反点数 | 1点加点 |
| 反則金 | なし(行政処分のみ) |
| 備考 | 警察の職務質問・取締り(検挙)の対象になります。累積点数がたまると、免許停止や免許取消しの可能性も。 |
バイク走行時にヘルメットを着用しないで警察官の取締りにあった場合、以下のような罰則を受けます。
よくある誤解
バイクのヘルメット着用に関する「よくある誤解」に、以下のようなものがあります。
- 「原付はヘルメットいらない」
- 「半キャップでもとりあえず被ればOK」
- 「ひもを締めてなくても被っていれば大丈夫」
- 同乗者がヘルメットなしは運転者に責任がない
それぞれどのような誤解なのかを詳しく見ていきましょう。
誤解1. 原付はヘルメットいらない
原付バイクに乗る場合、ヘルメットの着用はいらないという誤解がありますが、原付であってもヘルメットの着用は必須で、着用しないと交通違反となります。
1986年(昭和61年)以前は、原付のヘルメット着用は義務化されていませんでしたが、原付も含めた死亡事故が頻繁に起きていたことを背景に、原付にもヘルメット着用義務化が拡大。
すべてのバイクでヘルメットが義務化され、原付を含めバイクの排気量に関係なくヘルメットの着用が義務付けられています。
誤解2. 半キャップでもとりあえず被ればOK
半キャップを被ってバイクに乗っても違反にはなりませんが、万が一転倒した際は、頭部や顔を守りきれず大きな障がいとなることもあります。
高速道路や風の強い日に半キャップで走行していると、ヘルメットが頭部よりずれたり、外れたりしやすく、ヘルメットとしての機能も果たせません。
バイクのヘルメットは転倒の際に、打ち付けると致命傷になりやすい頭部や顔面を守るために装着するもので、ファッション性を優先するのは、安全性の観点から本末転倒です。
誤解3. ひもを締めてなくても被っていれば大丈夫
バイクのヘルメット着用は義務付けられていますが、あごひもを締めるまでは規定されておらず、あごひもを締めなくても違反とはなりません。
しかし、バイクのヘルメットは転倒などで頭部を打つ場面において、頭部や顔面を守る役割があり、あごひもを締めないと転倒時にすっぽぬけて頭部を強打する可能性があります。
転倒時などの万が一の際に頭部を守るには、あごひもを締めることが必須なので、ヘルメットを被るだけでなく、しっかりあごひもを締めましょう。
誤解4. 同乗者がヘルメットなしは運転者に責任がない
2人乗りができるバイク(排気量51cc以上のバイク)は、後席に人を乗せて走行(タンデム走行)できますが、運転者のみならず後席の同乗者にもヘルメットの着用義務があります。
バイクに乗って走行する場合は、搭乗者すべてにヘルメット装着の義務が発生し、同乗者がヘルメットを装着しないで警察の取締りにあうと、運転者に罰(違反加点1点・反則金なし)が科されます。
また、万が一同乗者に怪我をさせてしまった場合は運転者に責任も生じるので、可能な限り同乗者にも安全な服装や装備をさせた上で同乗走行をしましょう。
法的に認められるバイクヘルメットの基準

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/BC-6288958/
ヘルメットにはさまざまな種類のものがありますが、ヘルメットであればOKという訳ではなく、以下の表のように、バイク走行に適したヘルメットを選ぶ必要があります。
| 番号 | 基準内容 | 解説 |
| 1 | 左右及び上下の視野を妨げない構造であること | 周辺確認ができないと、安全運転が困難になるため。ジェット型やフルフェイス型は基本的にクリア。 |
| 2 | 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げない構造 | ひさし部分が柔らかすぎると走行中に下がって危険。 |
| 3 | 聴力を著しく妨げない構造 | 車の接近音やクラクションが聞こえる程度の通気性・聴覚性が必要。 |
| 4 | 衝撃吸収性を有し、帽体に耐貫通性があること | 転倒時や衝撃時に頭部を保護できる構造。発泡スチロール素材を使用しているものが多い。 |
| 5 | 衝撃により容易に脱げないようにし、あごひもで固定できる構造 | かぶるだけでなく、あごひもを締めていないと脱げやすくなるため、違反となる可能性あり。 |
| 6 | 重量が2kg以下であること | 重すぎると首に負担がかかり、安全面で不利。通常は1.5kg以下が多い。 |
| 7 | 人体を傷つけるおそれのある構造でないこと | トゲや鋭利な装飾、金属製の突起物はNG。理由は、事故時に怪我を助長するため。 |
参照元:e-gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
ヘルメットを被った際に、左右上下の視野が確保でき、風圧でひさしが垂れて視界を妨げない構造のものを選ぶ必要があります。
また、聴力を著しく妨げない構造である必要もありますが、視界が確保できないと安全走行ができず、聴力を妨げると回りの車やバイクなどの存在に気づきにくく危険です。
ほかにも衝撃吸収性があり、転倒時に頭部を保護する構造である必要があり、あごひもでしっかり固定できて、転倒時に脱げるような構造もNGになります。
上部の表のような条件を満たしていないと、バイク用のヘルメットとしては安全面がクリアできないので、工事現場用のヘルメットなどを被ってのバイク走行はNGです。
道路交通法施行規則第9条の5
道路交通法施行規則第9条の5では、ヘルメットの基準について定められています。
また、ヘルメットメーカー側が取得した安全性に合わせ、以下のようなマークがあり、ヘルメットを選ぶ際はこれらのマークが表示されたものを選びましょう。
- PSCマーク
- SGマーク
- JIS規格
それぞれのマークが何を表しているのか、詳しく解説していきます。

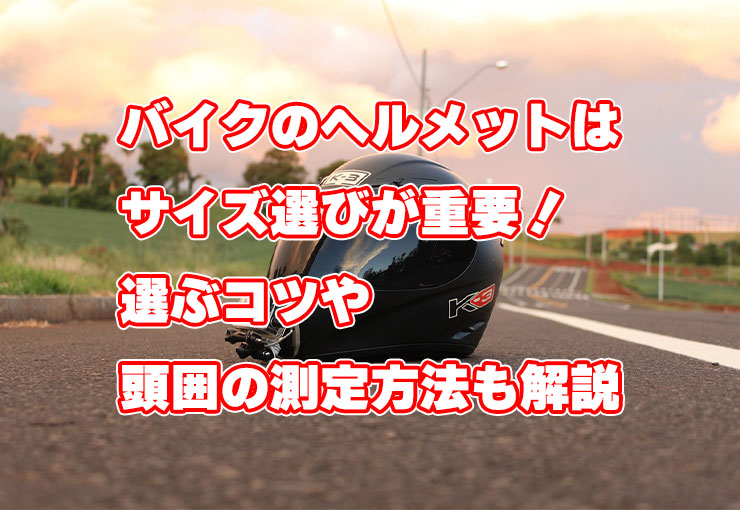

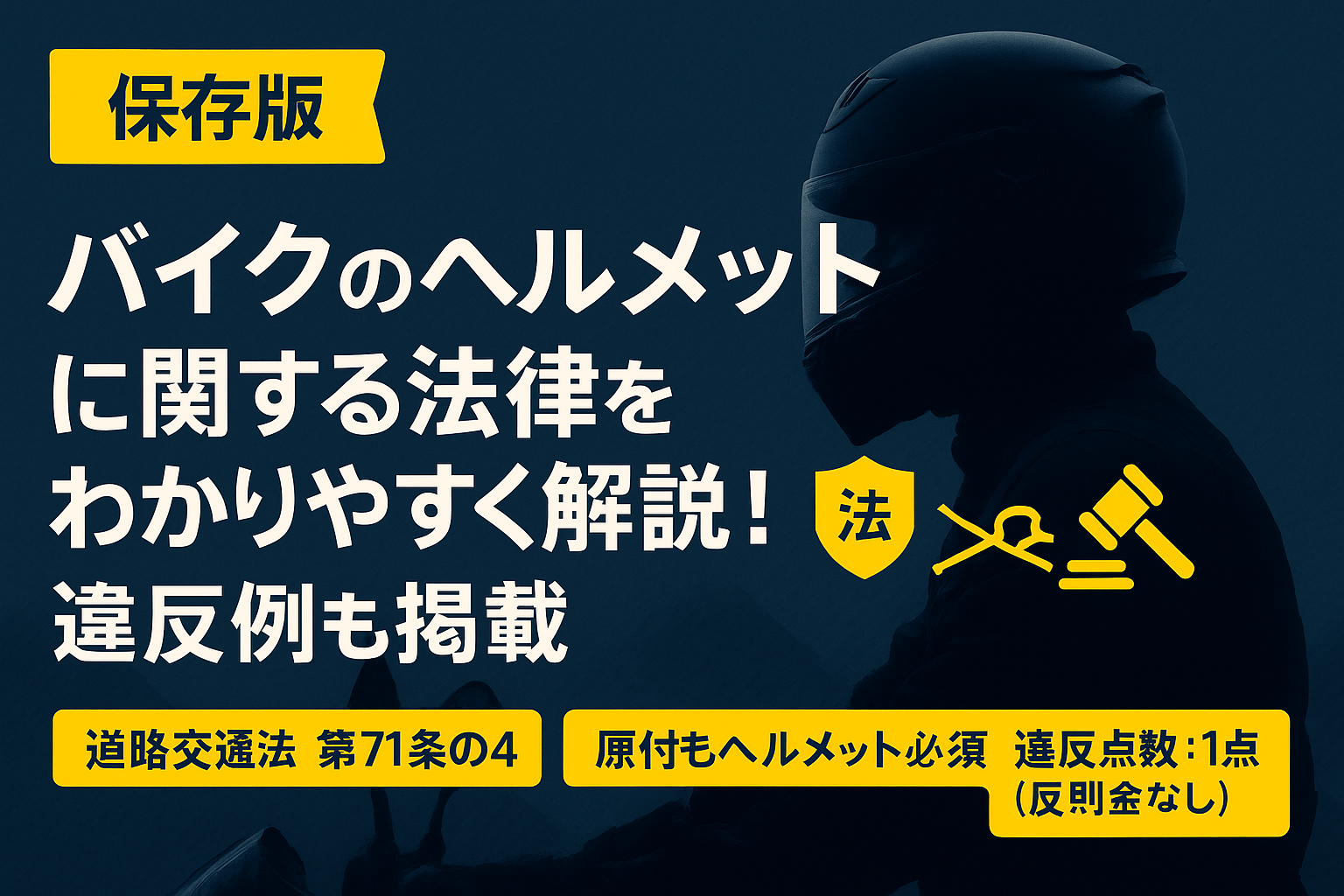
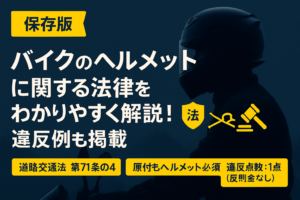









コメント