騒音を出すバイクの通報は運輸局へ

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/97-3285495/
騒音でうるさいバイクが迷惑な場合は、まず警察に通報することを考えると思いますが、110番通報すれば警察官が駆けつけてくれます。
また、慢性的に騒音を出すバイクがいて迷惑な場合は、警察に通報して対応してもらう以外にも、運輸局に通報を行うとより効果的です。
通報時に伝えたいこと
警察や運輸局に騒音のうるさいバイクの通報を行う場合は、騒音で迷惑を被った日時や場所、分かれば騒音バイクの車種や色、ナンバーも合わせて伝えます。
また、「#9110」に電話すると警察官が相談に乗ってくれるので、バイクの騒音問題に悩まされている方は、相談をしてみるのもよいでしょう。
運輸局に通報する場合も警察に通報する場合と同じで、日時や場所、バイクの特色やナンバーを合わせて伝えますが、バイクの車種やナンバーがないと対応が難しいので情報を得ておく必要があります。
通報しても騒音問題が解決しない場合
通報して効果が出なかった場合でも諦めず、何度も警察などに通報するのがオススメです。
騒音を出すバイクは警察に取り締まられるのを嫌がるので、騒音を出すと警察に通報されると思わせられれば、騒音を出すことも減ってくるでしょう。
効果がすぐに出ないかも知れませんが、諦めずに通報を続けると、騒音問題の解決につながるケースもあります。
通報者の情報は保護される?
警察に通報すると、「通報者としてバレるのでは」と不安に思う方もいるかも知れませんが、たとえ通報しても通報者の情報がほかに漏れることはありません。
また、運輸局に通報した場合でも、迷惑行為を行う者に対し、通報者の情報が漏れることはありませんので、騒音に耐えられないと思ったら安心して通報しましょう。
なぜ警察は取り締まらないのか

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/A1-1701179/
騒音バイクに対し、警察に通報しても解決に至らないことがあり、「通報しても無駄なのかな?」と思うこともあるかも知れません。
通報を受けた警察は現場に向かいますが、タイミングよく騒音バイクを取り締まるのが難しいため、騒音解決につながらないことがあります。
騒音に関する取り締まりが難しい
騒音がうるさいバイクは騒音測定を行ったうえで、違反となるかどうかの判断が行われますが、騒音測定にもルールがあり、駆けつけてきた警官が音量測定を行うのは難しいです。
ただし、下部でマフラーを切るなどしてわざと大きな音が出るように改造している場合は、消音器不備や保安基準違反などで取り締まりできます。
香川県の事例ですが、道路運送車両法などのあらゆる関係法令を適用した取り締りを行っているので、騒音を出す迷惑なバイクがいる場合は警察に通報してください、とあるので迷惑な騒音バイクがいる場合は警察に通報しましょう。
参照元:https://www.pref.kagawa.lg.jp/kocho/kocho/koe/k1626040225.html
(香川県:県民の声一覧)
警察が来る頃には走り去っている
騒音バイクがいて通報をした場合でも、警察官が現場に到着する頃にはすでに迷惑バイクが走り去ったあと、というケースもしばしばあります。
警察に通報したあと、警察官が現場に到着するまでにかかる時間は平均して8分程度となっており、8分あれば騒音バイクはその場から走り去ってしまうでしょう。
そのように、通報後に警察官が現場に駆けつけたけど、すでに騒音バイクが立ち去っていて対応できないケースが多々あります。
何度も目撃する場合は運輸局や自治体へ通報
騒音を出すバイクが近所にいたり、頻繁に目にしたりする場合は、運輸局に通報するのがよいでしょう。
また、マンションなどの集合住宅に騒音を出すバイクがいる場合、直接注意や話をつけようとするのは逆恨みなどのリスクがあるため、集合住宅を管理する業者や管理組合に通報しましょう。
ほかにも、役所には住民相談窓口や苦情に対応する窓口があるので、継続的に騒音に悩まされている場合は、役所に相談する手もあります。
基本的には自力救済禁止
法律には自力救済禁止の原則があり、例えバイクの騒音で悩まされ生活に支障が出ていたとしても、自分でバイクを破壊したり、バイクの持ち主に暴言を吐いたりするなどの行為は禁止です。
バイクに傷を付けたり、持ち主に暴言を吐くなど実力行使すると、行った側が器物損壊などの刑事罰を受ける可能性があります。
自分で解決をしようとせず、必ず警察か役所などで相談を行い、彼らを通して騒音問題を解決しましょう。
バイクの騒音規制の歴史

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/8A-500910/
バイクの騒音規制は年々厳しくなっていく傾向にあり、新車で販売されるバイクはより厳しくなった現行の規制に従わないといけません。
日本で最初に騒音規制として導入されたのが、意外と古く1952年からで、次の1971年規制から旧車と言われるバイクが含まれます。
<h3>1971年騒音規制値</h3>
| 定常騒音値 | 加速騒音値 | |
| 軽二輪(126cc~250ccまで) | 74dB | 84dB |
| 小型二輪(251cc超) | 74dB | 86dB |
1971年に導入された騒音規制値では、軽二輪(126cc~250ccまで)が、定常騒音値が74dBで加速騒音が84dBまで、251cc超の定常騒音は74dBで加速騒音は86dBまでとなりました。
定常騒音値とは、エンジン最高出力の60%の回転数で走行したときに測定される音量のことで、速度が50Km/hを超える場合は50Km/hで測定されます。
また、加速騒音値とは定常騒音値を測定する状態からフル加速を行い、10m進んだ地点で測定される音量のことです。
1986年騒音規制値
1971年規制から一気に厳しくなったのが1986年規制で、それまでの定常騒音値と加速騒音値に加え、近接騒音値も導入されました。
| 定常騒音値 | 加速騒音値 | 近接騒音値 | |
| 軽二輪(126cc~250ccまで) | 74dB | 75dB | 99dB |
| 小型二輪(251cc超) | 74dB | 75dB | 99dB |
近接騒音値とは、エンジンの暖気が終了した状態でギアをニュートラルにし、最高出力の75%(このとき回転数が5,000回転を超える場合は5,000回転)の回転数で行う測定方法のことです。
測定機の置く位置も定められており、排気方向から45度の角度で、7.5m離れた位置で行う測定方法を行います。
2001年騒音規制値
| 定常騒音値 | 加速騒音値 | 近接騒音値 | |
| 軽二輪(126cc~250ccまで) | 71dB | 73dB | 94dB |
| 小型二輪(251cc超) | 72dB | 73dB | 94dB |
1986年騒音規制値でも対応に追われ、大変だった国内のバイクメーカーでしたが、2001年規制では更に音量への締め付けが強くなり、規制値に対応できずに生産終了となるモデルも出ました。
定常騒音値は1986年規制から3dBしか変わっていないように見えますが、無音(0dB)と3dBをラジオに例えて比べると、3dBではハッキリと放送内容が聴き取れるレベルです。
規制値に収めようとバイクメーカーは、ゴムなどを使ってエンジンの振動音を消したり、チェーンカバーなどの裏に消音材を敷き詰めたりするなど、涙ぐましい努力を行っています。
2014年騒音規制値
2014年騒音規制では、バイク区分の名称がクラスとなり、クラス1から3の3区分となっています。
| 定常騒音値 | 加速騒音値 | 近接騒音値 | |
| クラス1(50cc) | 廃止 | 73dB | 廃止 |
| クラス2(125cc) | 廃止 | 74dB | 廃止 |
| クラス3(126cc超) | 廃止 | 77dB | 廃止 |
また、定常騒音値と近接騒音値が廃止となり、加速騒音値のみで測定されるようになりました。
新型車は2014年1月から規制、継続車(前年以前より販売されているモデル)は2015年1月から、輸入車は2016年1月から2014年騒音規制が導入されるようになっています。
2016年からは世界基準
2016年4月より施工された新基準では、2016年10月以降に販売されるバイクの排気音とマフラーに対し、国際基準に従った基準が採用されました。
この新基準により、基準を満たしていないバイクは新規登録を行えなくなり、新基準施工前に生産されたバイクは、性能や音量などを表記したマフラーを装着すれば新規登録が可能です。
道路運送車両法の保安基準も新基準に合わせて変更され、JMCA(一般社団法人全国二輪車用品連合会)によって認証されたマフラーか、純正マフラー以外は保安基準を満たしていないとみなされており、車検も通らなくなりました。
音量規制の範囲内であったとしても、認証マークのないマフラーを装着していると、保安基準違反で警察の取り締まり対象となっています。



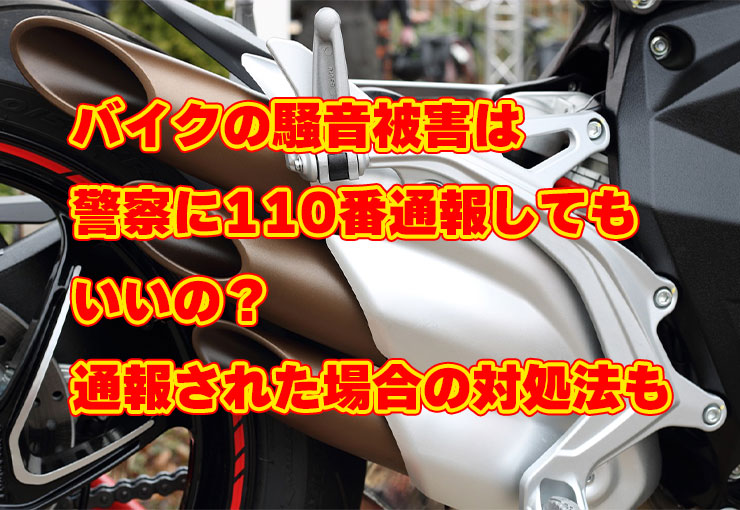
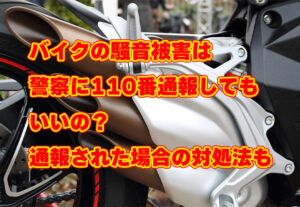









コメント