バイクの背もたれは構造変更検査に合格すれば違法ではない

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/80-4562069/
バイクの背もたれ(シーシーバー)は、保安基準の定めに反しない限りは、違法とはなりませんが、高さや設置方法などによっては違法となることもあります。
背もたれを取り付ける際は、保安基準や道路運送車両法で定められている範囲で取り付ける必要がありますが、範囲を超える場合は構造変更の届け出を出し、合格が必要です。
構造変更とは
構造変更とは、カスタムなどによって、登録時よりバイクの寸法や構造が変更される場合に出す申請のことで、申請がないままだと保安基準違反などで取り締まりの対象となります。
構造変更を行わないと取り締まりの対象以外にも、車検にも通らなくなるので、車検のあるバイクは早めに手続きを済ませておきましょう。
なお、構造変更が必要なのは車検が必要な250cc超のバイクで、250cc以下のバイクが行う手続きは「改造申請」となり、変更があった場合は改造申請を行わないと取り締まりの対象となります。
構造変更(改造申請)が必要になるケース
カスタムなどで以下のようにバイクの寸法や構造が変更となった場合は、構造変更(250cc以下は改造申請)が必要です。
- 車体の長さが3cm以上変更となったとき
- 車体の幅が2cm以上変更となったとき
- 車体の高さが4cm以上変更となったとき
- 重量に50kg以上の変更があったとき
- フレームカットなどによって強度に変更があったとき
これらの変更があった場合、変更を行った日から15日以内に構造変更(改造申請)の手続きを行い、合格しなければなりません。
車検のあるバイクの場合、構造変更手続きを行って合格となった日から2年後が車検の満了日となるので、合格の日時点で車検の残り日数があっても残り日数は抹消となるので、注意が必要です。
構造変更手続きの手順
構造変更手続きを行うのは、住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で、バイクを持ち込んで手続きを行います。
構造変更の申請には、以下の書類が必要となるので、手続き日にバイクと合わせて持参しましょう。
- 自動車検査証
- 自動車検査票
- 申請書(2号様式:ダウンロード可能)
- 自動車重量税納付書
- 納税証明書
- 点検整備記録簿
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 使用者と所有者の委任状(代理に手続きを行ってもらう場合)
- 構造変更申請書
- 手数料納付書
手数料や手続きの流れ
バイクの構造変更に必要な手数料は、自動車審査証紙1,600円と、自動車審査証紙500円の合計2,100円です。
必要な書類と手数料を持参の上、運輸支局の窓口で構造変更の申請を行い、審査が終わると自動車審査証紙が届きます。
自動車審査証紙が届いたらバイクの検査を行うので、運輸支局のwebサイトか電話から検査の予約申し込みを行い、検査日にバイクを持参して車検と同様の検査を受け、合格したら新しい車検証と検査標章(車検シール)を受け取って完了です。
構造変更を行ったら保険会社にも連絡
バイクの構造変更手続きを終えたら、忘れずに保険会社に構造変更を行ったむねの連絡を行いましょう。
カスタムなどで構造変更を行った場合は、保険会社に連絡を行う通知義務があり、もし連絡を怠ると事故の際に保険金の支払いが困難になることがあります。
リスクに応じて保険料が決められているため、保険料が変更となる場合もありますが、構造変更を行ったら必ず保険会社に連絡をしましょう。
【OK/NG】違法になりやすいバイクカスタムの種類

引用元:https://pixabay.com/ja/photos/A4-3110175/
道路運送車両法などで定められている範囲内であれば、基本的にはカスタムをしても申請の義務がなく違反になりませんが、寸法や構造が変わっていなくても、違法となるケースもあります。
違法となってしまわないよう、違反となるカスタム事例を紹介していきますので、カスタム時の参考にしてみてください。
マフラーの違法カスタム
マフラーの排気音には規制があり、平成22年より施行されている現行の規制では、バイクの排気量によって出せる音量が異なっています。
第一種原付クラス(50ccまで)は近接が84dBで加速が79dBとなっており、第二種原付(50~125cc)は近接が90dB、加速79dBです。
軽二輪自動車(125~250cc)は近接が94dBで加速82dB、小型二輪自動車(250cc超)は近接が94dB、加速82dBとなっています。
排気音がこれらの数値を超える場合は違法となりますが、バイクが製造された年式によって騒音の基準が異なり、基準は次のとおりです。
排気音量はバイクの年式によって異なる
現在では排気量によって規制音量が異なっていますが、バイクの年式によってその時期に施工されていた規制が採用されます。
| バイクの年式 | 適用される音量規制 |
| 1985年以前に製造 | なし |
| 1986年~2000年に製造 | 250cc以上は99dB以下 |
| 2001年以降に製造 | 250cc以上は94dB以下 |
| 2014年以降に製造 | 車種の基準値+5dB以内 基準値が79dB以下ならば84dBまで |
| 2016年以降に製造 | マフラーに基準適合を証明するマークが必要 |
例えば、旧車と言われる1985年以前のバイクは、当時に音量規制がなされていなかったため、現在の音量規制からは除外の対象です。
また、2016年以降に製造されたバイクには、騒音規制に適合している証としてマフラーに証明マークが必要となり、バッフルなどの消音機器を取り付けて規制をクリアするのも不可能となりました。
ナンバープレートの違法カスタム
2016年の法改正により、それまでナンバープレートは見えやすい位置に装着するとだけ定められていたのが、細かい規制が設けられました。
2016年以降では、ナンバープレートは見えやすい位置に装着する以外に、カバーで覆ったり、回転や折り曲げたりするなどの行為は全て違法となります。
ほかにも、ナンバープレートを横から見た場合、上向き40度から下向き15度までの範囲内で、上から見たときに角度が付いている場合も違法です。










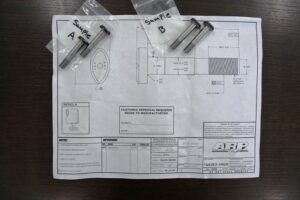



コメント